漆の新たな可能性を求めて
漆と家具といえば座卓で象徴されるように、家具全体を漆で仕上げたものが大半だった。
漆は大変に魅力的な素材だが、一方では複雑な工程と手間から大変高価なものになる。
だからというわけではないが、文房シリーズのデスクでは、全体を漆で仕上げることはせずに、あえてデスクトップに限って漆で仕上げるという部分使用を意図することで、漆の魅力を十分に生かしながら価格を抑えることを意図した。
錫蒔研ぎ出し

シリーズのデスクの中でハイエンド商品となるこのデスクトップは、黒の漆の上に錫を全体に蒔き、研ぎ出した独特の風合いを持つ天板で、現状のバリエーションの中では、最も手間のかかる仕上げだ。ちょっと見ると、金属のパネルのようにも見える不思議な表情でありながら工芸品としての格調を備えたデスクトップである。
高価といえば高価だが、同じ漆でも美術品と比べれば、むしろ安価とも言える。

このデスクトップに興味のある人は是非現物見本を見てほしい
漆は傷がつく
時折売り場に立っていると「傷つきませんか」という質問を受けることがある。
答えは「つきますよ」しかないのだが、かつて日本の家具のもう一つの代表であるちゃぶ台も、客間の座卓も上等なものは漆塗りときまっていた。ウレタン塗装などない時代だ。
使えば傷がつく、ただ自然素材というのは傷もまた景色になっていく。
もちろん大きな傷をつけた場合には補修が必要だ。
長期間使ってあまり気になれば、塗り直しや、補修を可能にするために、デスクの天板は取り外しできるようにデザインしている。大きな声では言えないが、天板を別な仕上げにすることも物理的には可能だ。
えらそうな事を言うようだが、前提として、ものを大切に使うという心遣いあってのことだと思っている。
漆
かつて漆のことを海外ではJAPANと呼ばれ、宝物のように珍重された時代があった。それほどに漆は日本を代表する工芸だったのだろう。漆のしっとりとした美しさと、様々な技法によって変化する表情が私たちを魅了する。
香川は日本有数の漆の里
この商品のメーカーである桜製作所の本拠地、四国香川では古くから漆芸が盛んで、蒟醤(きんま)、存清(ぞんせい)、彫漆(ちょうしつ)など数々の技法が継承されてる日本有数の産地だ。
プロジェクトでは香川県無形文化財保持者であり紫綬褒章の受章者でもある作家の山下義人さんの協力を得て「文房シリーズ」の漆のデスクトップの開発をしてきた。
一閑張りの技法をもとに土佐和紙の肌裏紙を用いて繊細でやわらかな肌合いをだしたもの、石肌を想わせる変塗りで独特な表情を見せる「石地塗」、そして全体に錫を蒔き、研ぎ出し磨き上げた「牡丹絞塗」のデスクトップは今まで目にしたことがない格調に輝いている。
こうした変り塗りは、漆の性質を生かしながら色彩と材料の応用で塗り肌にさまざまな表情が生まれ、堅牢性と実用性を兼ねた技法である。

発売当初はデスクトップの沢山のオプションをもち、その中から自由に選定できるようにしたが、どうも日本人というのは、沢山あると選定に困惑するようで2010年モデルから一気に3種類に絞り込んだ。
絞り込んだ理由は、もうひとつあって、それは売り場の売り子さんが説明しきれないという事もあったようだ。
特別な引出しの話

金物との決別
さまざまな部分で考えられる限り考えているが、その中でも特に思い入れが激しいのが引出しだ。
デザインにあたっての思い入れとして100年もつデスクをと考えた。実際に机を百年使う人はまずいないので現実味はないが、まあ強がりの心意気ぐらいに思って頂ければ幸いだ。
一般論だが機械は必ずと言っていいほど故障する。我が家のポンコツのシステムキッチンもまず金物から不具合が始まる。
道具の寿命を極限まで延ばすためには、故障しそうなものを使わないという最も原始的な方法がある。
今でこそ金属の引出しレールは一般的だが、普及し始めたのはそう昔のことではない。それまでは、そして数こそ減ったが今も、上等の桐箪笥や江戸指物などまるで空気を押すような見事な細工の引出しが、その技を競っている。

ということで、金物を使わないデザインとした。更に引出しの引き手も金物を使わずに指かけの穴で済ますことにした。さりとて昔の上等な桐箪笥のような細工は材料からしても技術からしても現実的ではないので、現在の製造工程で可能な製作方法としている。
引出しといえば、普通は立派そうな前板があり、その後ろに手抜きとは言わないまでも、塗装していない木地の箱がくっついているものだが、文房シリーズでは箱として全ての面を仕上げている。
そのまま机の上に出しても、どこから見ても抜いた引出しには見えない。
それがどうしたと言われれば、江戸の粋とでも答えておこうかと思っている。
ただしレールを使った引出しのようにストッパーはついていないので、そのつもりで引き抜けば落下する。


商品モデルでは緩やかな曲面とした。(下の写真参照)

もののクオリティはディテールの美しさの集積だと信じている
いくつかの特徴
最初にいくつかの特徴をまとめておこう。
コンパクトなサイズ
前述のとおり二月堂をコンセプトとしているが、まずデスクとしての必要な大きさの検討から始まった。最初のモデルは現状からすればずいぶん大きなものが検討された。(下の写真参照)デスクというのは不思議なもので、なんとなくイメージする大きさというのがあるし、社会的にも社長さんの机とか、代議士さんの机などステータスシンボル的な意味を持つ場合もある。

机の上に置いてある板が最終製品の大きさ
そんな、いわばデスクの副次的機能はさておいて、必要最小限の大きさを検討していった。結果幅90センチ、奥行き45センチと設定した。
この寸法に至ったもうひとつの理由は、大きなデスクを使っている人でも、実際に使用する面積というのだろうか、積み上げられた書類の谷間はそんなに大きくないということもある。
居間のコーナーでも、和室の片隅でも、廊下ですら置けるコンパクトなデスクが特徴だ。模様替えも、ちょっと力持ちなら一人で十分移動が可能だ。
筆返し コンパクトを補うディテール

コンパクトだが、デスクからものが落ちると困る。広く大きなデスクなら必要ない心配だろうが、このサイズだと少々気になる。
デスクトップの両サイドが、すこしだけ高くなっているのは、筆記用具や小物を不注意で落としそうになったときにストッパーとして機能するデザイン上のディテールで、単なる意匠ではない。
日々使ううちに、あるとないとでは大違いである事が理解できるだろう。
ご推察のとおり、ヒントは日本古来からある「筆返し」を現代に翻訳した。今風に言えば「ストッパー」とか「落下防止なんとか」ということになるのだろうが、「筆返し」とはなんとも心地よい表現だと思う。
普通のデスクでありながら
現実、お値段のことを言えば、驚くほどに安い家具やデスクは沢山ある。びっくりするほど高価な家具もある。
文房シリーズも決して安価な家具ではない。多分世の中には役割分担というのがあって、量産が得意な会社と、まったく量産が不得手な会社がある。
文房シリーズのメーカー 桜製作所は後者の象徴のような会社で、そもそも注文家具で60年やってきた会社だから、量産などやろうと思ってもできない。もちろん手仕事が多い分コスト高になるのだが、量産ではできないクオリティを求めている。
百年を意図して
使い捨てではなく、長く大切に愛用してもらえる家具を意図している。
あくまでも、ものの表現にしかすぎないが、百年使える家具を思ってデザインしている。
そのためには、飽きないデザインであることが必要だ。個性の強いデザインは使い手の気持ちの変化や感性の進歩の中で違和感が生じてくるものだ。
直線を生かしてできるだけシンプルなデザイン、そして基本モデルで黒を基調としたのは、どんな空間でも、まわりにどんな色がきても、けんかをしない色ということで設定している。
一見小さなただのデスクだが、よく見ると素晴らしい。使い続けるともっと素晴らしい。そんな商品を目指してディテールのクオリティに許される範囲で、とことんこだわっている。詳しくは、次ページをご参照願いたい。
文房というネーミング
シリーズの名前を「文房シリーズ」とした。古来、ものを書いたり、読書をする部屋を称して「文房」と言った。今で言えば書斎ということになるのだろう。
書の世界で文房四宝といえば筆、紙、硯、墨のことだ。おなじみの文房具というのは文房すなわち書斎で使う道具ということだ。
現代では、文房四宝に代わってコンピュータが文房具の主人公になりつつある。時代や道具が変わっても、身の回りのちょっとした用事のためのデスクは必要だ。
昔から文房具は「知」のための道具、そして文房は「知」を生み出す場所であった。
使い手が輝くための道具という思いを込めて「文房シリーズ」とした。

もうひとつの始まり 多足机のこと
毎年、極力都合をつけて正倉院展に足を運ぶことにしている。何度見ても多くの発見と学びがある。決して家具を見に行っているわけではないが、正倉院宝物の中で、家具に類する物はごく僅かしかない。
そもそも我々日本人の生活に家具というのはとても少ない。というよりほとんど無かったという方が正確だろう。
洋風化が始まるまでの家具といえば、少々極端かもしれないが箪笥とちゃぶ台ぐらいしか無い。昔の絵図を見てもおよそ家具に類する物は見あたらない。一方西洋では、古くから寝台や王の座る巨大な椅子など様々な家具を見ることができる。
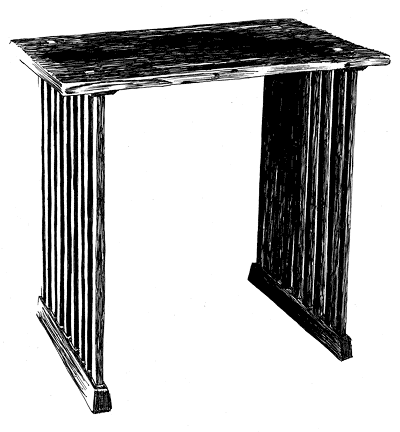
正倉院宝物に家具のたぐいが少ないのは、そんな理由もあろうと思っている。
宝物の中に多足机というのがある。なんとなく現在の神社で使われている机の原点のような気がするがどうだろう。
そのシンプルでありながら、多足というアイデンティティを持った美しさに驚くのだが、私の最大の関心事は、いったいこれをどうやって作ったのかという事だ。あらゆる機械工具に囲まれている現代では通り過ぎがちだが、まともな工具はおろか、刃物すらまれな時代、少なくとも鋸などの登場以前だ。是非知りたいと思っているがいまだにわからない。
今回の文房シリーズのシンボルとしてデザインしたデスクは16足机そのものだ。デザインに当たって、置かれる空間の制約をできるだけ排除したかった、要はどんな所に置かれても違和感なく存在できることだ。私見だが普通の四本脚のデスクは座敷の片隅に置くには違和感があるが、16足デザインは妙に和の空間にもなじむ、畳の座敷に置かれても美しいと思っている。

こだわりのパーソナルファーニチャー
「文房シリーズ」デザイン雑記帳
2010年2月、文房シリーズに新商品ラインが加わり、既存のデスクの細部のデザイン、仕様を変更して2010モデルが発表された。
これを機会に、開発当初からのデザインの背景を書きとめてきたメモを整理してみた。
以下、コンテンツの順番は、およそ思いつくままで、体系的なものではない。写真は下手な文章を補いたいとできるだけ掲載しているが、開発途中のモデルも含んでおり最終商品とは異なる部分も多々あることをご了解いただきたい。
はじまり 二月堂のこと
文房シリーズのそもそもの始まりは二月堂だ。日本の家具の代表である二月堂を現代に翻訳してデザインしたらどうだろうというのが発端だ。
若い人たちは二月堂といってもなじみがないかもしれない。ここで、ごく簡単に二月堂について説明しておこう。
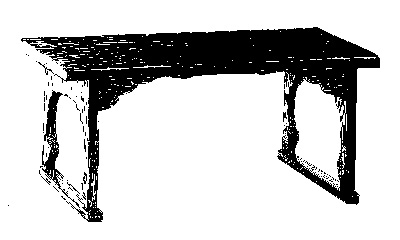
二月堂というのは小さな座卓だ。おおむね45センチ×90センチぐらいで、脚が折りたためるものもある。和室が少なくなって、その数激減だろうが、文机から料理やさんのお座敷まで現在でも多く使われている、いわばマルチパーパスの小座卓である。
二月堂の由来は、お水取りで有名な奈良の東大寺二月堂でお坊さんが食事をする食堂(じきどう)で使われたもので、正式には二月堂食堂机(にがつどうじきどうき)と言う。
お水取りは千二百年を超えて休むことなく継続されている、おそらく世界で最長の歴史をもつ祭りだろう。とすれば二月堂という小さな机も千年を超える歴史をもつことになる。さりとて、千年前の机を今も使っているということでは無いので誤解の無きよう願いたい。ただ現在の二月堂も、何代目になるのか知るよしもないが、千年受け継がれている原型に忠実に製作されていると聞いている。
本物は上記の現代二月堂と違って、お坊さんが質素な食事をとるための卓であり、大きさはおおよそ三分の二ぐらいのとても小さなものだ。
話を戻そう。二月堂は日本人の生活の中に脈々と受け継がれてきた。理由は単純で、とてもコンパクトなサイズと何にでも使える利便性、そして後に折りたたみ式という収納に便利な機能などに代表されよう。
現代日本の住空間は豊かになったとはいえ、まだ狭い。そんな日本の空間でも自分の居場所を作ることができる道具としての家具を意図して「文房シリーズ」をデザインしている。




 Inoh Ippei
Inoh Ippei Link
Link 0
0
 文房シリーズ デザイン雑記帳
文房シリーズ デザイン雑記帳 14:36
14:36
